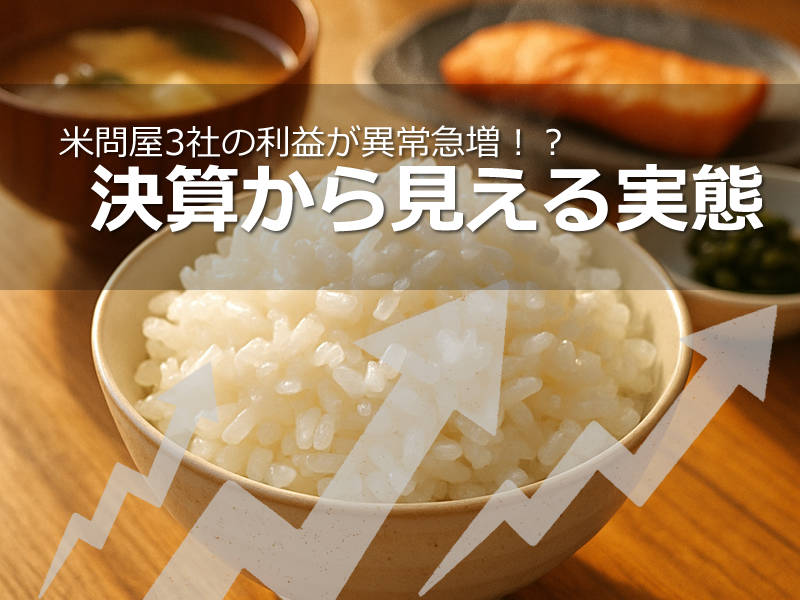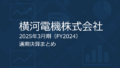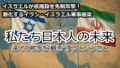2025年6月、小泉進次郎農林水産大臣が国会で「ある米卸業者は営業利益が前年比500%増」と発言したことをきっかけに、米卸業界の収益構造に注目が集まりました。本記事は2025年5月に初稿を公開しましたが、その後9月時点での確認と精査を経て、内容を一部修正・追記しています。
1. 木徳神糧株式会社(Kitoku Shinryo Co., Ltd.)
- 営業利益(前年同期):414百万円
- 営業利益(当期):1,853百万円
- 増加率:+348%(前年同期比で約4.5倍)
- コメント:営業利益が一気に4倍以上に膨らみ、常識的な範囲を超える増益として注目を集めている。
2. ヤマタネ株式会社(Yamatane Co., Ltd.)
- 営業利益(前年同期):Q1単体の公開数値はなし(部門別の推定値ベース)
- 食品事業では大幅増益が確認されており、報道では「500%超」との表現も
- コメント:利益急増の傾向は確かに見られるが、公式決算でQ1に限った「500%」を裏付ける数字は確認できず、詳細は依然不透明である。
3. 神明ホールディングス(Shinmei Holdings Co., Ltd.)
- 営業利益:非公開(非上場企業)
- 補足情報:備蓄米入札で大口落札を継続している点や、業界最大の供給ネットワークを持つことから、収益が拡大していた可能性はある。ただし、具体的な数字は不明。
異常な利益増の背景に何があるのか?
- 米価の高止まりと入札制度の影響:2024年〜2025年にかけて、政府備蓄米の放出や入札制度の運用方法により、卸業者が市場で優位な立場を得た可能性がある。
- 政策対応の遅れと在庫戦略:需要と供給のミスマッチ、また制度切り替え時期に生じた“制度の隙間”が一部で指摘されており、それを活かした戦略が利益急増につながった可能性もある。
こうした要因を踏まえると、2025年Q1における300〜500%という営業利益の急増は、単純な需要増では説明しにくく、“制度環境や市場構造に依存した収益の集中”と見られる余地がある。
結論:構造的成長ではなく、一過性の“スポット収益”の可能性
今回の増益は「市場のひずみ」を背景としたものであり、問屋側が本質的に収益構造を改善したというより、“仕入れタイミング”や“在庫戦略”に起因する一時的な利益であった可能性が高い。
とはいえ、この事例をきっかけに米卸業界の利益構造や透明性、さらには農政との関係性が改めて問われることになりそうだ。