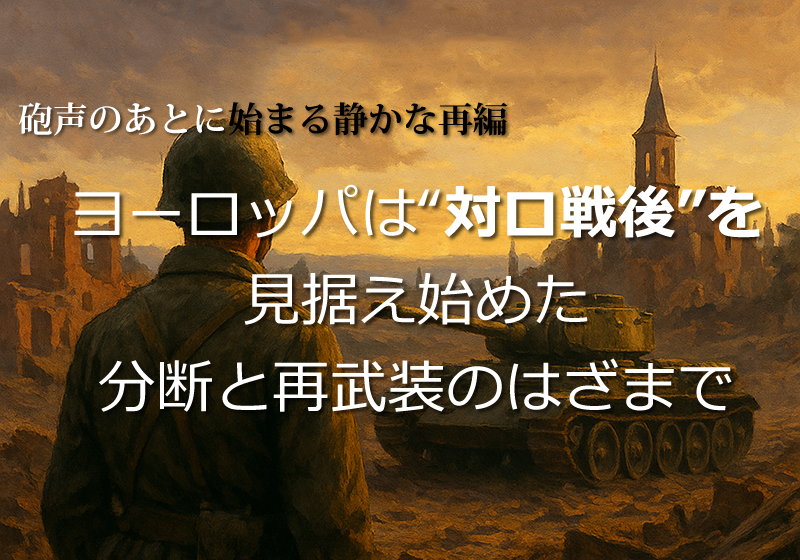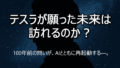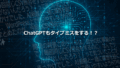ウクライナ戦争が始まってから3年が経とうとしている。かつての電撃的な進軍や大規模攻勢は影を潜め、戦線は膠着し、ドローン戦・塹壕戦・砲撃の応酬が日常となった。もはやこの戦争は停戦のタイミングすら失い、短期決着ではなく“持久戦”のフェーズに入っている。
この中で、EU諸国の視線は、戦後──すなわち「ロシアという隣国との再定義」に向きつつある。
軍備増強と「欧州版NATO」構想
ウクライナ侵攻によって、NATO加盟国に対するロシアの脅威が再認識され、東欧諸国(ポーランド、バルト三国、フィンランドなど)は劇的な国防費増強を進めてきた。
フランスやドイツも、これまでの慎重姿勢を変え、兵器調達やサイバー防衛に予算を振り向けている。特にドイツは「戦後最大の国防転換」と称される1,000億ユーロ規模の軍備計画を発表した。
その一方で、アメリカへの過度な依存から脱却すべく、「欧州版NATO(独自の安全保障機構)」を模索する声も強まっている。ただし、構想としての旗は立ったものの、加盟国間の温度差は依然として大きい。
分断されるヨーロッパ
EUは理念として「連帯」と「統合」を掲げてきた。しかし、ウクライナ戦争を巡るスタンスでは、加盟国間の温度差が顕著だ。
ポーランドやバルト三国は“対ロ強硬派”として最前線に立ち、ハンガリーやスロバキアは経済的・歴史的理由から、ロシアに対して一定の距離感を保っている。
また、ドイツやフランスも国内世論の変化を受け、全面的な支援から「慎重な支援」へと転じる兆しを見せている。
EUの防衛・外交政策は、統一よりも「連立」の性質を強めており、戦後のロシアとの関係性をめぐっても、一枚岩とは言い難い。
通商・エネルギー戦略の再構築
戦争の影響で、エネルギー・通商の面でも欧州は大きな転換を迫られた。
ロシア産天然ガスへの依存を減らすべく、LNG輸入や再生可能エネルギーへの投資が加速。さらに、中国との経済的関係も見直され、EVや半導体分野では米国寄りの通商戦略にシフトする動きが見られる。
これは米中対立の“欧州巻き込み型”とも言える構図であり、トランプ政権が再び登場すれば、ヨーロッパはさらに「自立と依存」のはざまで苦悩することになる。
ドイツ経済の葛藤──エネルギー・インフレ・軍備・株価
ヨーロッパ最大の経済国・ドイツは、ウクライナ戦争による影響を最も強く受けている国の一つだ。
まず、戦前にロシア産天然ガスに大きく依存していたドイツは、戦争勃発後にエネルギーコストの急騰に直面した。とりわけ化学・金属・製造業などエネルギー多消費型産業は厳しい環境に置かれ、2023〜24年の経済成長率はユーロ圏最低水準に沈んだ。
このエネルギー供給不安に加えて、インフレも深刻化。ドイツの消費者物価指数(CPI)は一時7%を超え、家計と企業の両方に圧力をかけた。ECB(欧州中央銀行)の利上げが続いたことも、企業投資や住宅市場に冷や水を浴びせる形となった。
しかし2025年に入り、ドイツ経済はやや様相を変えつつある。エネルギー価格の安定や対中輸出の回復期待、欧州版グリーン投資政策への資金流入を背景に、株式市場は上昇基調を見せている。ドイツ株価指数(DAX)は過去最高水準を更新し、一部では「インフレを乗り越えた資本主義の回復力」とも称されている。
とはいえ、楽観視はできない。再武装のための巨額支出は内需を圧迫し、軍備の多くを米国から輸入している現実は、経済波及効果を限定的なものにしている。
中国との経済依存も解消されておらず、米中対立が激化した場合、ドイツはその“板挟み”に立たされる可能性が高い。
対ロ戦後の「地政学的再定義」
ウクライナが完全にロシアを押し返すことは難しいとしても、停戦や部分的な合意によって一定の区切りが訪れる可能性はある。そのとき、ヨーロッパは「ロシアをどう位置づけ直すのか」という根本的な問いに向き合う必要がある。
制裁を続けるのか。緩和するのか。防衛ラインをNATOの枠内に留めるのか、ウクライナを含めた“新NATO”を構想するのか。
ヨーロッパは今、戦場の向こうにある「外交・経済・安全保障」の大地図を書き換え始めている。
その作業は、いわば「戦後処理」の準備段階であり、戦争の“勝利”ではなく、“次の秩序”を見据えた冷静な再構築である。
──分断と再武装のはざまで。ヨーロッパの選択は、世界の次なる秩序の出発点となるかもしれない。