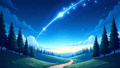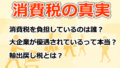「お米が高くて買えない」──そんな声が聞こえてきた2024年。日本はようやく長いデフレの時代から揺れ動き始めている。
振り返れば、好景気に乱舞したと言われる昭和バブルは1980年代の出来事であり、あれからすでに45年が経過している。現代の2025年を生きる僕らの多くは、その熱狂を知らない世代だ。むしろ社会に出たときにはすでにデフレが常態化していて、人員削減やコストカットが正義とされていた。
巷には100円ショップが増え、300円の牛丼や100円マックが象徴するように「安さこそ正義」という空気が社会を覆っていた。その空気を吸って育った僕らは、無意識のうちにこう刷り込まれたのだ。
デフレ脳──待てば値下げが訪れる、辛抱すれば報われる
という暗黙のルール。
それが僕らの思考を長年縛ってきた。
📈 変わりゆく時代のサイン
しかし、いま日本の風景は変わりつつある!
- 📊 33年ぶりに高値を更新した日経平均は42000円を超え、日本企業は再評価されている
- 💵 賃上げが広がりはじめ、物価上昇率を上回れば庶民の暮らしは劇的に変化する
- 🏦 金利も、わずかではあるが上昇に転じた
さらに、🌾 米の価格までもが前年比で大きく上がっている。「食卓の主役すら安泰ではない」、都内の新築マンション販売平均価格は1億円を突破。2025年前半では1億3000万円をも超えている。この現実は、デフレ脳に生きてきた僕らにとって衝撃の連続かもしれない。
⏳ 時間の意味が逆転した
デフレ時代は、待てば得をする世界だった。
- 🛍 型落ちセール
- 📦 在庫処分
- 💸 値下げ競争
「待つ」ことが美徳であり、戦略だった。
だがインフレ時代は違う。
待てば価格は上がり、損をする。
「待つ」ことは怠慢であり、喪失になる。
同じ“時間”が、時代の変化によって真逆の意味を持ち始めている。
🧭 政府が「デフレ脱却」と言えない理由
ではなぜ、政府はいまだに「デフレ脱却」を公式に宣言していないのか?
そこには慎重な理由がある。
政府が重視するのは、以下の4つの指標だ。
- 📈 消費者物価指数(CPI)
- 🏭 GDPデフレーター
- ⚖️ 需給ギャップ
- 👷 ユニット・レーバー・コスト(ULC)
この4つすべてがプラスで安定的に続いたとき、初めて「デフレ脱却」と宣言できる。
現状、CPIやGDPデフレーターは明らかにプラスだが、需給ギャップやULCはまだ揺らぎが残る。
経済再生相も「タイミングを誤ればデフレに逆戻りする」と慎重姿勢を崩さない。
つまり、「脱却」と言葉にすること自体が、大きな責任を伴うのだ。
🌱 デフレ脳からの脱却
僕らに求められているのは、この変化をどう捉えるかだ。
- ⏩ 「待てば得」から「他人よりも先に選ぶ勇気」へ
- 📈 「値上げは悪」から「値上げは成長の証」へ
- 💳 「借金は気軽」から「金利はリスク」へ
デフレ脳という洗脳から解き放たれなければ、僕らは新しい時代に取り残される。
🔮 インフレ時代の選択
- 🏦 預金には金利がつく
- 📊 株式市場や投資商品が上昇しやすい
- 🏠 金や不動産価格も上昇している
これは単なる経済の話ではない。
生き方そのもの、時間の意味そのものを切り替えることに他ならない。
✨ 結び
インフレの訪れは、ただの数字の変化ではない。
それは、僕らが「時間」をどう感じるか、「未来」をどう選ぶかという、根源的なマインドの転換を迫っている。
デフレの時代を生き抜いた僕らが、新しい金利のある時代をどう歩むのか。
その答えを探す旅は、もう既に始まっている。