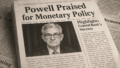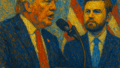1980年代後半、日本は狂乱のバブル景気に包まれていた。
株価は3万8千円を突破し、東京の地価は「アメリカ全土を買える」とまで揶揄された。
誰もが信じていた──この繁栄は永遠に続く、と。
だがその裏で、静かに引き金が引かれていた。
そしてその後30年間もの長い停滞が待ち受けているなど、誰も想像していなかった。
📉💥 日銀の急ブレーキ🏦⚡️
1989年5月、公定歩合は2.5%から3.25%へ引き上げられた。
その後6月に3.75%、10月に4.25%、12月には4.75%と段階的に上昇し、翌1990年8月にはついに5.25%へ到達。
わずか1年余りで合計2.75ポイントの引き上げという歴史的な急上昇である。
本来なら段階的に抑えるべき熱狂を、日銀は一気に冷やしにかかった。
結果は──株価の暴落、不動産の急落、銀行に積み上がる不良債権。
「失われた30年」の序章は、こうして始まった。
🇺🇸🦅 FRBの慎重さ🛑📈
一方、2020年代のアメリカ。
コロナ後の急激なインフレに直面したFRBは、同じ選択肢に迫られていた。
だがパウエル議長は、批判されながらも「遅い」と言われるほど段階的に利上げを進めた。
- 📊 0.25%刻みの引き上げ
- 💬 常に市場との対話を重視
- 🌐 景気後退を避けつつインフレを鎮静化
その姿勢は、1989年の日銀とは正反対だった。
🔄📉 歴史は繰り返すのか?⏳
いま日本は長いデフレの時代を抜け、インフレ局面に差しかかっている。
資源価格の高騰、円安、賃金上昇が重なり、物価上昇は現実のものとなった。
「デフレ脱却」への期待と同時に、舵取りを誤れば再び奈落に落ちかねないという不安も広がっている。
歴史は繰り返す。二度と同じ轍を踏んではならないのだ。
✨🌍 未来への結論と問いかけ🤔🚀
バブルを潰した日銀、AIを育てたFRB。
二つの中央銀行の選択は、国の未来を大きく分けた。
では、次の選択の時が来たとき──
僕らが選ぶ道はどちらなのか?
それとも、まったく新しい第三の道を描けるのか?
そして今の私たちならば、インフレに直面した時にどのような思考で対処すべきか──その答えを導き出せるかもしれない。