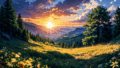長く続いた“眠り”だった。中央銀行の支えのもと、日本の株式市場はゆるやかに、しかし確かに回復の道を歩んできた。だがいま、静かにその支えが外れようとしている。ETFという「夢のような買い支え」が終わり、日本経済は“自らの足で立つ”フェーズに突入しようとしている。
🏦 銀行株売却──2002〜2010年の買い支えはどうなった?
2025年7月、日本銀行は2002~2010年に金融安定化を目的として購入していたメガバンクなどの銀行保有株を、保有残高約1兆3500億円のうち550億円を残してすべて売却し、長期保有してきた銀行株からの撤退を完了させた。
この政策は、当時の金融危機への対応として約2.4兆円を投じた異例の措置であり、銀行システムの安定化を目的としていたもの。保有期間中に受け取った配当収入なども含めれば、日銀は最終的に充分な利益を得る形で回収する結果となった。
📉 静かに消えていくETF買い支えの時代
また、日銀が長年保有してきた日本株ETFの売却も進み、現在残されているのはわずか550億円程度とされる。これは、かつて70兆円規模にも膨らんだETF保有残高から見れば、ごく小さな規模だ。市場はもはや、中央銀行の支えに頼らずとも、安定と成長を続けられるという自信を得つつあるのだ。
🔁 なぜETF買い支えは始まったのか?
きっかけはリーマンショック、そして東日本大震災による景気後退だった。デフレ脱却を掲げた安倍政権下、2013年からのアベノミクスとともに、日本銀行はETF買い入れ政策を導入。
そして2016年、英国のEU離脱(Brexit)ショックやマイナス金利政策の行き詰まりを背景に、ETF買い入れは年3.3兆円から6兆円へと倍増。これはアベノミクス第2ステージの象徴的施策だった。
中央銀行が株式市場に直接介入するという世界でも異例の措置により、日本株市場は下支えされ、企業業績や雇用にも波及したのだった。
🧪 10年に及ぶ“支え”の時代と批判
ETF買いは“株価維持のための麻酔”だったのか?
この問いは、10年間の間に幾度となく繰り返されてきた。市場の健全性を損なう、企業のガバナンスが歪む、売却時に大きなショックが来る──そんな声が常につきまとっていた。
しかし結果的に、2025年の日銀売却は「静かに」「ほぼ最高値で」「市場に動揺を与えず」に行われた。そして今なお、マーケットは動じていない。これを「出口戦略の成功」と見る向きもある。
📈 4万円を超えた日経平均と、新たな支え手
皮肉にも、日銀が「支え手を降りた」今、日本株はその真価を問われている。新NISA制度の普及、海外投資家の資金流入、企業の株主還元や構造改革──そうした“民間”の力が、株式市場を支える時代が訪れている。
ETFに依存した相場は終わり、投資家たちは新たな指針を探し始めている。これからは、成長戦略や国際競争力が真に問われる「実力主義のマーケット」が始まるのだ。
🌅 ETF買い支えという夢の終わり、そして目覚める日本経済
中央銀行が買い支えた10年は、もしかすると「日本経済の集中治療室」だったのかもしれない。過去の痛みを癒し、自力で歩き出すための時間を稼いだ。その役割を終え、いま日本経済はようやく目を覚ますときが来た。
ETFという夢が終わる。そして、夢から醒めた日本は、これから何を見て、どこへ向かうのか。
いま、日本経済は底を打ち、上昇し羽ばたく準備が整っている。新しいステージに進む力は、すでに私たちの中にある。
このチャンスを掴み、ともに成長するかどうか──それは、私たち一人ひとりの“行動”にかかっている。