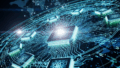「失われた30年」「経済成長できない日本」──最近よく耳にする、ちょっと気の滅入る言葉たち。先の参議院選挙のときにもよく聞いたフレーズだ。ネガティブだし、本来ならばあまり聞きたくはない。
でも、そうも言っていられないのが現実。毎日の買い物のレジでお会計を見るたび、ギョッとするような物価の高さに驚かされる方も多いはず。
そんな中で、いつも決まって聞こえてくるのが「インフレ率2%を目指す」というお決まりのフレーズ。もはや“聞き慣れた常識”としてスルーされがちだけど……ちょっと待って?
その「2%」って、一体誰が決めたの?本当に正しい数字なの?
気になって調べてみたら──なんとびっくり。ちゃんとした根拠、ほとんど無いらしい。
えー!マジか!?
そんなツッコミを真面目にぶつけてみたくて、今日はこの「2%神話」にメスを入れてみようと思う。一緒に、知られざる経済の裏側を覗いてみませんか?
🇳🇿 世界で最初の「インフレ目標」──まさかのニュージーランド!?
世界に「インフレ目標」という考え方が広まったのは、実はそんなに昔の話ではない。
そして、最初にこの目標を明確に打ち出した国がどこか、知っていますか?
アメリカでも日本でも、経済大国と呼ばれる国々ではありません。
なんと──南半球の牧歌的な国、ニュージーランド🇳🇿だったのです!
1980年代、ニュージーランドは年間15%を超えるような、とんでもないインフレに苦しんでいました。物価がジェットコースターのように上がり、国民の生活は混乱の極みに。
この反省から、彼らは中央銀行の独立性を強化し、大胆な政策「インフレ目標制度(Inflation Targeting)」を導入します。
そのとき、彼らが目標とした数字が……「0〜2%」というインフレ率でした。
この上限**“2%”**というラインが、奇しくも世界のスタンダードになっていく、まさに歴史の転換点だったのです。
🤔 2%は「ノリと空気」で決まったってホント!?
さあ、ここからが一番面白いところ。なぜ「2%」だったのか?
驚くことに、ニュージーランド準備銀行の当時の総裁であるドン・ブレイシュ氏自身が、後にこう語っているのです。
「2%という数字は、厳密な経済理論から導き出されたものではなく、むしろ政治的に“受け入れやすい”現実的なラインだった」
これ、どういうことか分かりますか?
つまり、「なんとなくこのくらいが良さそうじゃね?」っていう、空気と感覚と、当時の政治的判断が多分にあったってこと。
もちろん、デフレに逆戻りしないための**「安全弁」や、物価統計の「誤差」を吸収する**意味合いも考慮されてはいましたが、
ガチガチの数理モデルから導き出された「完璧な最適解」ではなかった、というのが実態です。
「えー!そんなアバウトな理由で、世界中の経済が振り回されてるの!?」──そう思わずツッコミたくなりませんか?
🌍 そして「2%信仰」は世界へ…まるでシンボルのように
ニュージーランドがこの制度でインフレを抑え込むことに成功すると、その成功に続き、
90年代にはカナダ、イギリス、スウェーデン、オーストラリア…といった国々が次々と「インフレターゲット2%」を導入していきます。
そして、世界の経済をリードするアメリカ(FRB)ですら、2012年になってようやく正式に「インフレ率2%」を目標として明言。
でもこのときも、その背景にあったのは「理論的な最適化」よりも、
市場との対話をスムーズにするための“シンボル”としての2%
だったと言われています。
つまり、「使いやすいから」「みんなが使ってるから」「説明がしやすいから」──
そうやって、ひとつの“数字”がひとり歩きし、やがて世界の経済が信じる「前提」になってしまったのです。
まるで、何かの宗教における「聖なる数字」のように、深く疑問視されることなく受け入れられてきた側面があるのかもしれません。
💡 まとめ:数字の「裏側」と経済の「調和」を見つめ直そう
「2%」という数字は、確かに便利で、直感的で、ある種の安心感を私たちに与えてくれます。
でも、それはいつの時代も、どの国にとっても正解な**“絶対的な数字”じゃない**。
考えてみてください。かつて中国は、2%をはるかに超える5%以上のインフレ率でも、驚異的な経済成長を遂げていました。
なぜなら、そのインフレは所得の増加や国内の旺盛な消費意欲を伴っていたから。つまり、物価が上がっても、それ以上に国民の豊かさが増している実感があったんです。
時代が変われば、経済の構造も、人々の生活様式も、そして金融政策の優先順位も変わってくるはず。
先進国が目指す2%と、新興国が目指すインフレの「適温」は、必ずしも同じではないのかもしれません。
大切なのは、数字の表面だけを追うのではなく、
そのインフレが「良いインフレ」なのか「悪いインフレ」なのか、そして経済全体の「調和」がとれているか
を見極めること。
だからこそ私たちは、
「なんとなく信じてた数字」を、いま一度、自身の頭で問い直す勇気を持っていいんじゃないでしょうか?
🌀そして、ふと湧き上がる新たな疑問──
もし2%という目標が、ただの「数字合わせ」に過ぎないのだとしたら──
今この2025年の日本にとって、本当に目指すべき「適温」とは、一体何パーセントなのだろう?
「インフレ率は常に2%であるべき」
その前提が揺らぎ始めた今、世界は静かに、新たな基準を模索し始めています。